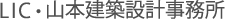壁2015.10.26
この外壁は水平距離で90センチ分斜めになっています。このように斜めにした理由は、この壁の前に庇を作りたかったからです。ただ、スッキリとしたファサードにするために庇と分かるものでなく、その庇の機能を兼ね備えてくれるようにと壁を斜めにした訳です。内側の空間もその分広げることができます。
この斜めの壁の下に入れば、雨の日も玄関や勝手口にも濡れずに行くことができます。もう一つは汚れ防止にもなりますね。
向こうに見える三角のものは勝手口引き戸、黒い土間はカラーモルタル、石は各務原の山の砕石。
玄関2015.10.21
玄関の事例
この住宅の玄関は写真では分かりづらいかもしれませんが、ドアが二重になっています。外のドアはガラス製ドア、その内側には木製ドアを設けています。一つのドアを入られても、もう一つのドアにいたずらされているときに外から見えるように外側をガラスにしています。
やや高い位置に玄関がありますので、防犯上、二重ドアを提案しました。ドアホンはインターホンを押さなくても人が近づけばセンサーが作動し自動で録画するタイプのものを併用し防犯カメラの役目として採用しました。
二世帯住宅 玄関2015.10.20
二世帯住宅
二世帯住宅の各世帯の設備構成、距離感はそのご家庭により様ざまです。住まい手の想いで造ることがよいと思っています。別居から、二世帯住宅の新築を機に同居を始められる場合には分からないこともあり不安もあるのは当然ですし、家族の理解度もそれぞれです。そのような場合には私は、初めは距離をとって生活できるプランに将来距離を縮めることが容易にできることを盛り込んでご提案しています。(例えば、各世帯を行き来するには玄関から、あるいは勝手口を向かい合わせにして、屋根を掛けておく。外の空間に出るのが互いに面倒になれば、その屋根の下に壁と床をつくり内部として繋ぐなど。)中にはもっと距離を縮めてくださいと言われることもありますが、そのときは、行き来がしやすい、子供が自由に行きかえるプランにしていきます。
二世帯住宅は将来に渡り家族構成の変化も大きいので、このことも考えつつご相談しています。ご主人の親と同居する場合と、奥様の親と同居する場合でもプランは変わってきます。
◆今回は二世帯住宅の玄関についてご紹介いたします。
玄関は一つ、別々、一つだけど中に入って別々になっている、などがありますが、下の写真は外の門の役割のあるドアを入ると通り庭が真っすぐに伸びて、その通り庭に面して各世帯の玄関が離れているプランの二世帯住宅です。
外からは一つに見えますが、中に入るとは玄関が分かれています。中では水回り前の廊下が各世帯を繋いでいます。
通り庭に面した玄関 外の入り口は一つ
建築材料 ガルバリウム2015.10.16
ガルバリウムには数多くの曲げ加工とその張り方、表情があります。この住宅は岐阜市岩田坂で設計したもので、南面はガルバリウムの横張りです。
・形状
大きく分けて、縦に張るもの(縦に張るものは横にも張れます)、横に張るものがあります。それぞれに、加工の仕方により釘が見えるもの、見えないものがあります。釘が見えないものは、重なる部分が大きくなりるのと複雑になりますので、面積当たりの単価は高くなります。釘が見えなくなる加工をしたものをスパン加工といいます。
形状はそれぞれフラットになるもの、よく見かける凸凹のもの、凸凹の平らな部分が大きいものなどがあげられます。
・特徴
ガルバリウムは鉄からできています。鉄の表面にアルミ亜鉛合金メッキ+焼き付け塗装が施されています。メーカーの説明書にはもし表面に傷ができてこのメッキがはがれた場合には傷の周囲にあるアルミ亜鉛がその傷を覆うように移動していくので、錆にくいとあります。一度、移動するところを見てみたいものです。
建築材料 スターライトパネル(アクリル製)2015.10.15
アクリルでできたパネル(商品名スターライトパネルt36)をご紹介します。規則的に見た目複雑に成型したアクリルの芯材の両面にアクリルの板を貼った材料です。
ハニカム構造ですので、とても強度が高く、扉やテーブルの板、パーティションとしても使用できます。特徴は光を通しますので、その反射がとてもきれいな材料です。材料は透明ですが、複雑に成型されているため、向こう側ははっきりとは見えません。
写真は引き戸に使用したものです。スターライトパネルの小口にアルミ材を付け、戸車をつけています。
平屋2015.10.14
平屋はプランの自由性が高く中庭の配置や床の高低差を設けたりすることも容易です。
オープンガレージを備えた住宅です。費用の面もありますが、ここでは、向こうの景色を透すようにしています。
また、周りは畑に面しており虫が多いことと、防犯性を高めるため、風の通る雨戸をデッキの外に設けています。
キッチンと寝室の間には別経路で廊下があり、ご夫婦それぞれの書斎コーナーが廊下に面して仲良く並んでいます。
平屋2015.10.07
平屋の建築費のことを書きます。
平屋は高くなると聞かれた方は多いと思います。
40坪の2階建てと40坪の平屋を比較に出され、屋根、基礎が倍の大きさになるなど聞くと、何故か納得してしまいますね。
しかし、40坪の2階建てを平屋にすると、面積が小さくてすむのです。
・階段がなくなり 1,2階分で2坪減
・廊下も2階の分がなくなり2坪減
・トイレで1坪減
これだけ床面積が少なくてすむことも十分あります。
ということは、40坪の2階建てと比較するなら35坪の平屋ということになりますね。
平屋はそんなに高くなるということはありません。
平屋か躊躇されてる方は、一度、平屋でプランをしてもらわれると良いかと存じます。
ご参考に。
里の家 撮影2015.10.01
一昨日、里の家の撮影をしていただきました。
久しぶりに天気に恵まれ、予定日に撮影が出来てほっとしています。
里の家は木の表し箇所が程よくあり、温かみを感じる住まいとなりました。
スキップフロアーで4層の床レベルを構成し視線の広がりと空間に豊かさを創りだしています。
ちなみに障子の向こう側は物干しとなっています。
リビングから一段下がった向こうはスタディコーナーです。
オープンハウス2015.08.22
今日、明日と浜松でオープンハウスを開催しています。お施主様のご厚意に感謝申し上げます。
4台分のガレージがある家です。
南側にマンションがあるので、そこからの視線をかわすように格子を設けています。
敷地は周囲との高低差があり、がけ後退が必要でしたができる限り法面で対処しています。
大屋根の家2015.08.21
大屋根の家
敷地の南側に隣家があります。
庭を囲ってプライベートな空間を作るというほど近接していませんし、
そのような希望はありませんでした。
また、北側には金華山と岐阜城を望むことが出来ます。
このような条件から次のカタチにしています。
この家は南の方が平家で北の方が2階建てのプランです。
屋根は1枚で南から北に登るように大屋根になっています。
リビングは2階の空間につながっています。
大屋根の中にはベランダもあります。
![3_convert_20150608190115[1]](https://www.liclic.jp//wp-content/uploads/2015/08/3_convert_201506081901151.jpg)
![17_convert_20150608185743[1]](https://www.liclic.jp//wp-content/uploads/2015/08/17_convert_201506081857431.jpg)
![9_convert_20150608190502[1]](https://www.liclic.jp//wp-content/uploads/2015/08/9_convert_201506081905021.jpg)
スタンプコンクリート2015.08.21
先日、車庫の土間コンクリートにスタンプを施工しました。
手順は次の写真の順です。
1.スタンプするためのゴム型
![IMG_1528[1]](https://www.liclic.jp//wp-content/uploads/2015/08/IMG_15281.jpg)
2.打ったばかりのコンクリリートに色粉を万遍なく振り掛ける。
![IMG_1533[1]](https://www.liclic.jp//wp-content/uploads/2015/08/IMG_15331.jpg)
3.コンクリートが少し固まったところで、ゴム型でスタンプし、木目を形成していく。
![IMG_1534[1]](https://www.liclic.jp//wp-content/uploads/2015/08/IMG_15341.jpg)
4.ゴム型を外したら、木目が3Dで浮き上がったように形成されました。
![IMG_1535[1]](https://www.liclic.jp//wp-content/uploads/2015/08/IMG_15351.jpg)
5.形成された木目 お見事。
![IMG_1536[1]](https://www.liclic.jp//wp-content/uploads/2015/08/IMG_15361.jpg)
この後、別の黒っぽい色粉を振り掛け、浮き上がった部分の色粉を除去する工程が残っています。
後日完成写真を掲載します。 ツヅキヲヨム
オープンハウス2015.07.22

7月18日19日に浜松市の平家の住宅のオープンハウスを開催させていただきました。
お施主様のご厚意に感謝しております。
このキッチンも下引き換気扇となっているため、上に換気扇がないため、とてもスッキリとしています。
整風版は電動で昇降するようになっていますので、下げた状態では写真の通りカウンターもフラットでスッキリ。
スタンプコンクリート2015.06.02


今回は車庫の床にこのスタンプコンクリートというもので土間コンクリートを仕上げることになりました。
パッと見板ですね。
コンクリートを打ち均したところで、この木目を成型する金属の正にスタンプを大きくしたもので、このような模様を付けた後に着色をするものです。
以前は公共施設の外部などに使われることが多かったように思います。
出来上がりは、後日に。
キッチンの床下換気方式2015.05.29

整流板が収納されてキッチンもスッキリ
下の写真は整流板が電動式で出てきているところ。
既にこの方式の換気扇は数年前から数件造ってもらってますが、引きは問題なく使用出来ています。

このお宅おキッチンはスッキリ感を出すため換気扇フードを付けずに、床下に排気を引き込み外に排出する方法としています。
換気扇は市販のシロッコファンをキッチンの中に入れてます。
キッチンの上も下もシンプルな出来栄えは気持ちいいでよ。
製作はキッチンマインド
スキップフロアーの平家2015.05.22
一昨日、スキップフロアーの平家の撮影がありました。
傾斜地に建つこの平屋は、家の中のフロアーが4段になっています。

ダイニングテーブル:カッシーナ
チェア:カルテル社マスターズチェア
ペンダントライト:トムリクソン

チェア:イームズLCW
本棚:カルテル社

リビングからダイニングを眺める、その向こうに和室

えごの木2015.05.15
事務所のえごの木が満開を迎え、ご覧のように毎日、花弁が落ちてきます。
下向きに咲く花弁はとても綺麗です。
でも、掃き掃除の仕事が毎日増えますね。地面が土ならいいのですが。
これから、この花の数だけ実がなり、その実も毎日のように落ちてきます。
なので、施主様にはお勧めしていません。
花が綺麗で植えましたが、このような狭い場所には不向きした。

工事中に工務店が自己破産2015.03.25
今年の1月20日に岐阜の中堅の建設会社が自己破産したことは新聞などでご存じの方は多い
かと存じます。
私の場合は、その前の晩に知人からそのような内容を知らせる電話が入り、その晩はあまり眠
ることが出来ませんでした。
何故なら、その工務店が施工の上棟後数週間経過した現場があったからです。
工事中の破産は初めての経験でした。
新聞にその記事が掲載され、事実であったことを確認し、朝一で施主様に会いに向かいました。
事情を説明し、といっても破産したから何もできないという現状を受け入れていただくことと、私
と一緒に完成に向かってやっていくことを互いに確認しました。
後ろ向きのことを考えても、何も進まないので、一緒に踏ん張る想いを一つに出来たことは、そ
の後の進め方に勢いが出たと後から感じました。
皆様もあまり経験することがないことと存じますので、時系列順にその進捗結果を書いてみようと思い
ます。
1.M社への過払い金の実態の把握
上棟時に支払われている金額と出来高を査定してみると、数百万円の過払いが分かりまし
た。
年末に上棟したばかりで、まだ屋根が葺き終わってない、サッシが取り付いていない、この
工事分が過払いとなっていました。
2.工事請負契約書を確認する。
契約時に完成保証という保険に加入することにしてあったのですが、その手続きがされて
いるか確認する。
住宅あんしん保証様に確認したところ、加入の確認が出来ました。
その数日後には、住宅あんしん保証様が鑑定人を同行して現場の出来高状況の確認に来
てくれました。
今回の住宅では、この完成保証に加入していたことが過払い金、出戻り工事費用などを保
険金として支払われるため、継続工事を金銭面でサポートしてくれました。
<完成保証とは>
①過払い金と認められた金額(但し、上限はあります)と、引き継ぎ工事をした場合に一部出
戻って工事をしなくてはならない場合に、その費用を保険金として支払われます。
3.破産申立人の弁護士事務所に連絡を取る。
1.中に入ってよいか?
2.屋根、壁にはビニールシートで養生をしてあるが、更に養生をしてよいか?
3.今後はどうなるのか?
などなど
4.引き継いでくれる工務店を探すというより、私からT社に頼み込み、引き継ぎの見積もりを依
頼する。
快く引き受けていただき感謝しています。ただ、出てくる見積もり金額は気になりました。
5.足場業者に連絡をとる
足場業者は、足場の保全のため現場にその会社のものである旨の表示をされたので、連絡
をして意向を聞いた。
出来れば、引き継ぐ工務店に使用してほしいとのことであった。但し、料金は未徴収なので、
費用は全額出してほしいとのことであった。(その後そのようになった)
6.完成保証から、出来高査定が届き、チェックして返送を何度か繰り返す。
7.施主様は過払いの債権を放棄することで、弁護士事務所宛てに工事請負契約の「解除通
知」を送付し、M社との契約を解除した。この解除で、工事途中の建物が施主のものとなる。
(過払い金の債権の保全をする場合には、破産管財人が決定して、そこから全体の債権、資
産の算定を行い、数か月時間がかかるとのことであった。今回は破産管財人が決まる前に
手続きを行い、時間を要さなかった。)
8.3月7日、T社と続きの工事請負契約を締結し、工事再開となりました。
見積もり金額も大きくはオーバーせずに短期間でできたことは感謝とともに大変嬉しく思って
います。(途中にも屋根の再養生をしてもらったりと)
9.出来高査定の確認を住宅あんしん保証様と現場でする。
住宅あんしん保証様は出来高の実情に則り、粛々と査定していただけたこと感謝しています。
そして、今は普通に工事が進んでいます。施主様も一安心され、私もほっとしました。
傾斜地の家2015.03.19
午前中に傾斜地の家にお邪魔してきました。
壁のEP塗装の入り隅部の隙間の直しの作業の確認のため久しぶりにお伺いしたのですが、奥様がインテリアのお仕事をされてます
ので、一つ一つの生活用品がとてもセンスあるものばかりで取り揃えてあり、心地いい空間を満喫させていただきました。
4月に撮影を予定させていただきましたので、そのころには写真をアップできると思います。
外壁は杉板ですが、庇があるので、ほとんど変化なくきれいなままでした。
外構は奥様のお父様が本職でとてもいい樹形の木が自然な雰囲気を醸し出していました。
この家は、緩やかな斜面をそのままの地形を利用して、スキップフロアーで平屋ですが、空間に変化がありとても好きな家です。